点と点がつながる瞬間
浮かび上がる“共犯関係”の輪郭
社内労務監査チームが動き出してから、2週間が経った。
佐野を中心とした調査チームは、複数の店舗の売上・現金記録・勤怠表を照合し続けていた。
「どうしてこのズレは、いつもこの2店舗だけなのか?」
そんな小さな疑問から始まった検証だったが、やがてそれは、確かな“パターン”として浮かび上がってきた。
搾取が疑われる〇〇店だけでなく、隣接する〇×店、〇△店でも同様の端数誤差が見つかる。しかも、売上帳簿と現金報告にズレがある日には、必ずエリアマネージャーA(勤続5年)が訪店していた。
「Aが関わってるのは間違いない。だが──彼1人では、帳簿の整合性まではごまかせない」
佐野の疑念は、ある勤務記録を見た瞬間、確信へと変わる。
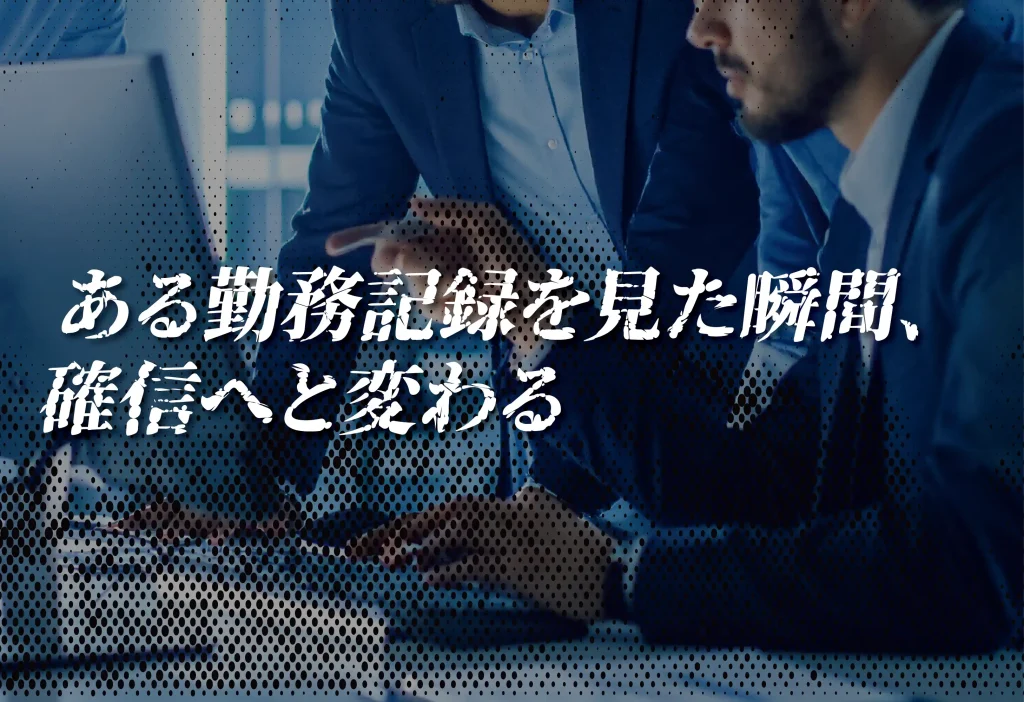
不審な“交互訪店”が浮かび上がってきた
その日、〇〇店の帳簿と現金に明らかな乖離がありながら、Aの訪店記録がなかったのだ。
「これは……Bが入ってる」
もう1人のエリアマネージャーB(勤続12年)。Aの先輩格であり、長年にわたって現場と本部の橋渡し役を担ってきた人物だ。
この店舗だけは、Bの名前が記録されていた。AとB、2人の行動パターンを照らし合わせると、不審な“交互訪店”が浮かび上がってきた。
「役割分担していますね。搾取のローテーションです」
佐野の読み通り、金銭ズレが発生する日はどちらか一方が訪れ、もう一方はその前後の処理を“帳尻合わせ”していた。
さらに追い打ちをかけたのは、経理部の久保が提出した1枚の社内決裁書だった。
「見てください、この伝票。売上のズレを“店舗側の入力ミス”として処理しろという指示。しかもこの手書きの指示、専務の筆跡です」
社内で絶大な影響力を持つ専務取締役Cの名が、初めて調査線上に浮かび上がった。
確認すると、同様の“修正指示”は過去1年で計8件。いずれもAまたはBが関与した店舗と一致していた。
「まさか……隠していたのか? いや、むしろ隠してやっていたのか?」
佐野たちの頭に、共犯関係という言葉がよぎる。
現場で金を抜くAとB、その報告をごまかすための帳簿操作を正当化するC。
この三者が連携して動いていたとしたら──これは単なる「不正」ではない。
組織的な搾取と隠ぺいだった。
物証は揃い始めていた。
あとは“確定”させるための一撃、核心を突く何かが必要だった。
次回へ続く…
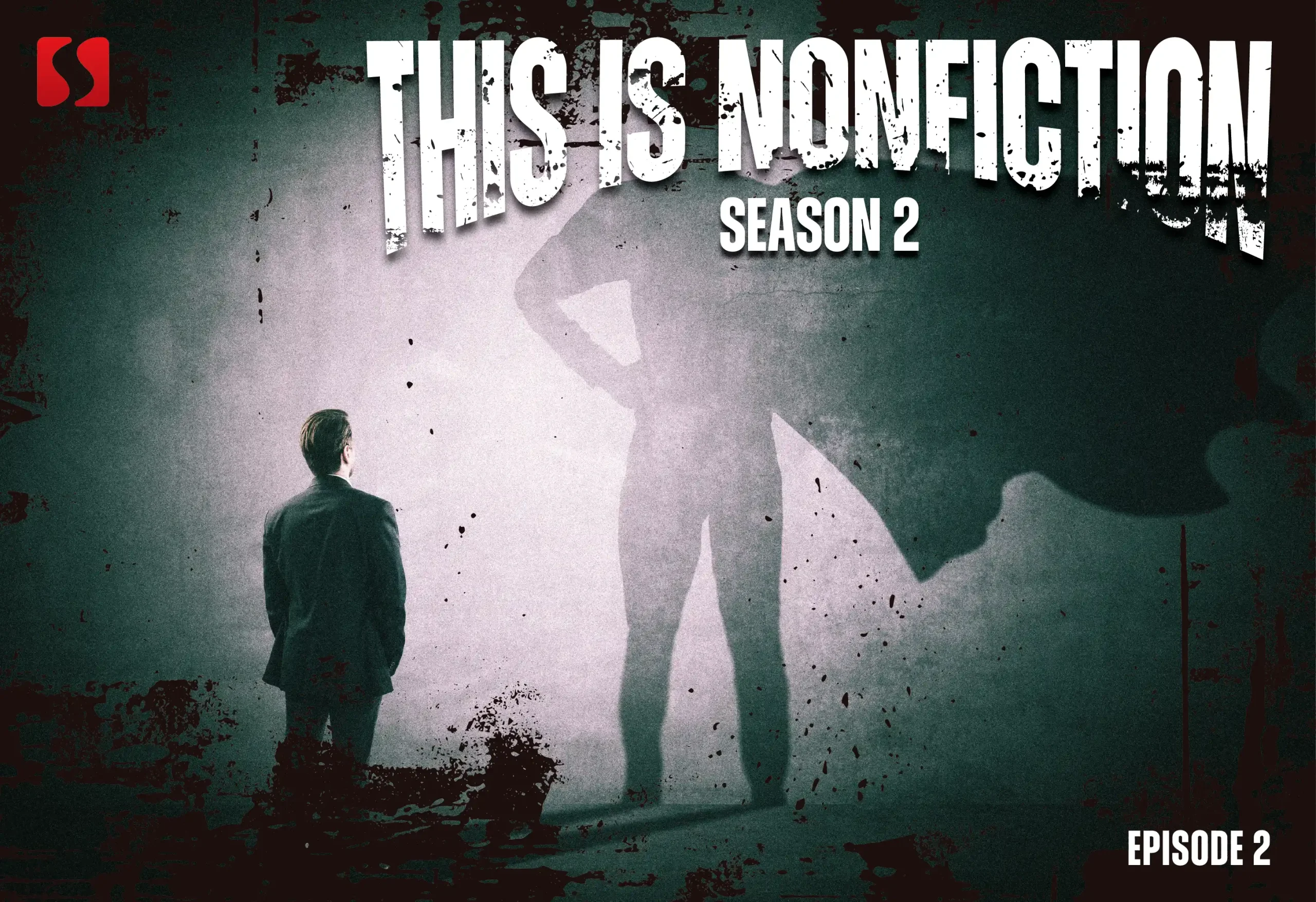
この記事へのトラックバックはありません。