これ、うちのコードと、ほぼ一致しています
開発部門の一角で、元CTOの椅子にいた男がそう言った。
その声には驚きというより、どこか疲れ切ったような諦めが混じっていた。
彼は、Y氏が入社する少し前まで、この会社の根幹システムの設計と品質管理を担っていた人物だ。
上場準備が本格化する直前、突然の退職を選んだひとりでもある。
私が持ち込んだのは、ある外部企業が最近公開したSaaS系システムのデモ版。
そのコードの一部が、社内のとあるプロジェクトで開発されたフレームワークと異常なまでに似ていたのだ。
「変数の命名規則、無駄な空白、コメントの癖──これは偶然じゃない。
“中の人間”が関わってないと、あり得ない」
彼の目が、ゆっくりと虚空を見据える。
私は黙ってうなずいた。
ついに──確信に変わる瞬間が来た。
流出の痕跡
その“外部企業”は、Y氏が社内で進めていたいくつかのプロジェクトの関連資料で何度も登場していた。
形式上は外注でも取引先でもなく、単なる「情報共有パートナー」という曖昧な立ち位置。
しかも、不思議なことに、そこに関する正式な契約書や請求書が一切存在していなかった。
代わりに見つかったのは──
社内サーバに存在する、暗号化されたログイン履歴と、一部“削除されたはずのメールの断片”。
復元ツールを使い、私たちが入手したログにはこう記されていた。
from:Y***@******
to:shoji***@△△△systems.jp
subject:例の仕様、更新版
添付ファイル:requirements_final_v3(.zip)
送信時刻は深夜2時。
会社のネットワークを経由して、個人の外部メールから送られていた形跡。
さらに添付ファイルの中身は、社内でも機密扱いだった開発仕様書と一致していた。
この時点で、Y氏による組織的かつ計画的な情報流出の可能性は限りなく黒に近くなった。
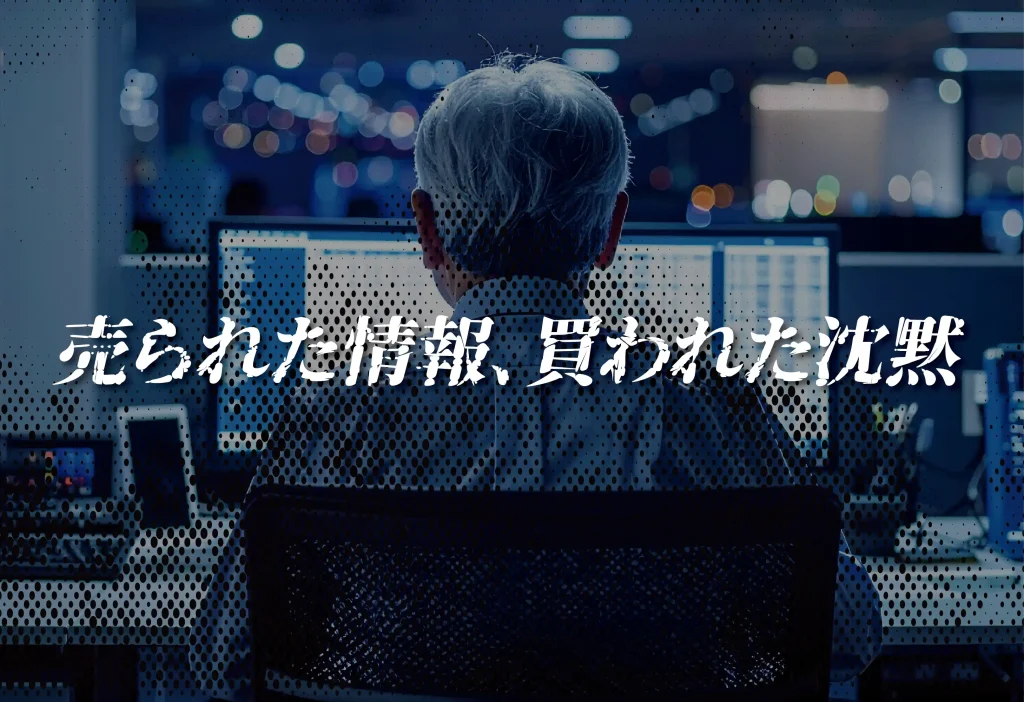
売られた情報、買われた沈黙
我々が注目した“外部企業”は、設立して間もない小さな法人だった。
だが奇妙なことに、公開するサービスの精度は極めて高く、価格も競合の半額近い。
裏を取ると、その企業の代表は、Y氏と同じ大学の研究室出身者で、
卒業後もしばしば交流があった形跡があった。SNSでは繋がっていなかったが、
共通の知人とのタグ付けや旧Facebookアカウントでの交信履歴が、わずかに残っていた。
つまり──
Y氏は、自社の知見とコードを使って、
仲間の外部企業に“流す”ことで、対価を受け取っていた。
社内の人間には「提携」や「情報連携」として処理し、形式的な書類は残さずに。
ただ、成果だけがその外部企業の名義で“市場に先んじて”登場する。
そして、浮いたリベートは会社の会計処理には一切出てこない。
資産ではなく、“人間の信頼”が盗まれていた。
会社を、壊すために登りつめた男
なぜY氏はここまで綿密に仕組んでいたのか?
これは単なる副収入目的のスパイ行為ではない。
彼が仕掛けていたのは、この会社を「乗っ取る」ための下地作りだったのだ。
■ライバルとなる人材は心理的に追い込み、自ら退職へと導く
■弱みを握り、社内での忠誠を得た人物だけを周囲に置く
■業績を上げ、株主の信頼を得て経営会議に影響力を持つ
■そして、情報を外に流しつつ、自社の競争力を意図的に下げる
結果的に、会社は上場の要件を満たせず、資金調達は困難に。
そのタイミングで“友好的な買収提案”が外部企業から届けば──経営陣は、選択の余地を失う。
つまり、Y氏は、この企業を“肥え太らせた上で壊し”、外部に吸収させることで、
完全に自分の掌に収めようとしていたのだ。
私たちが見ていたのは、“最初から仕組まれていた崩壊”
数々の違和感、消された声、すり替えられた記録、
そして繰り返される“偶然”の裏には、ひとつの明確な意思があった。
あの企業が誇っていた“成功”も、“売上”も、“人材”も──
そのすべてが、あるひとりの冷徹な計算の上に成り立っていた。
沈黙は、支配されていた。
未来は、売られていた。
だが、まだ終わってはいない。
私たちしえんグループの仕事は、ここからが本番だった。
次回へ続く…

この記事へのトラックバックはありません。