沈黙を破ったその先で
社内監査報告書の最終ページに、私はこう記した。
「Y執行役員による長期的かつ計画的な情報流出と、組織内部への心理的支配の痕跡を確認。
本件は、経営陣を含む社内コンセンサスによって、即時対応と抜本的な人事体制の見直しを要する。」
提出を終えたその夜、私はまっすぐに帰宅せず、会社近くの公園に立ち寄った。
曇天の下、ベンチに腰かけると、ようやく身体が重さを思い出したように、ぐったりと沈んだ。
私たちが見てきたのは、完璧に偽装された“成功の皮”の下に眠る静かな崩壊だった。
だが、ここからが始まりだった。
経営陣の沈黙、そして覚悟
報告書を提出した翌日、臨時の経営会議が開かれた。
資料に目を落とす役員たちは、沈黙を保ったまま、ページをめくる手が止まらなかった。
「……Y君を、信じていました。彼がいなければ、今の会社はなかった。だけど──」
沈黙を破ったのは、創業社長だった。
目の下に深い隈をたたえ、しばらく口を閉ざしていた彼は、やがて静かに言った。
「──この会社が失ったのは、金や情報だけじゃない。
“信用”だ。
それを、もう一度ゼロから取り戻さなければならない。」
会議室に、誰かの鼻をすする音が微かに響いた。
だが、誰もその顔を見なかった。
Yの排除、組織の再構築へ
Y氏は、社内調査結果と証拠を突きつけられた直後に、役職辞任と退職を申し出た。
形式上は「自己都合」だが、実質的には解任処分に近い。
そして後日、彼が暗に関わっていたとされる外部企業に対しても、
情報漏洩・背任の疑いで民事告訴が行われた。
同時に、経営陣は“再出発”を社内外に公表。
情報セキュリティ体制の刷新、匿名性の高い内部通報制度の導入、
そして「人を信じすぎないことを恐れずに制度化する」という明確なメッセージを出した。
もう、同じ過ちは繰り返さない。
その決意が、経営陣にも、社員たちにも、表情として、態度として、
少しずつ滲み出ていくようになった。
そして、再び歩き始めた
あの騒動から数ヶ月。
私たちしえんグループは、再び彼らのオフィスを訪れた。
驚いたのは、変わっていたのが制度だけではなかったということだ。
社員の誰もが、どこか顔を上げて話すようになった。
以前はどこか“静かすぎた”フロアに、今は小さな雑談や冗談が飛び交っている。
会議室のガラス窓には、誰かがマーカーで書いた言葉が残っていた。
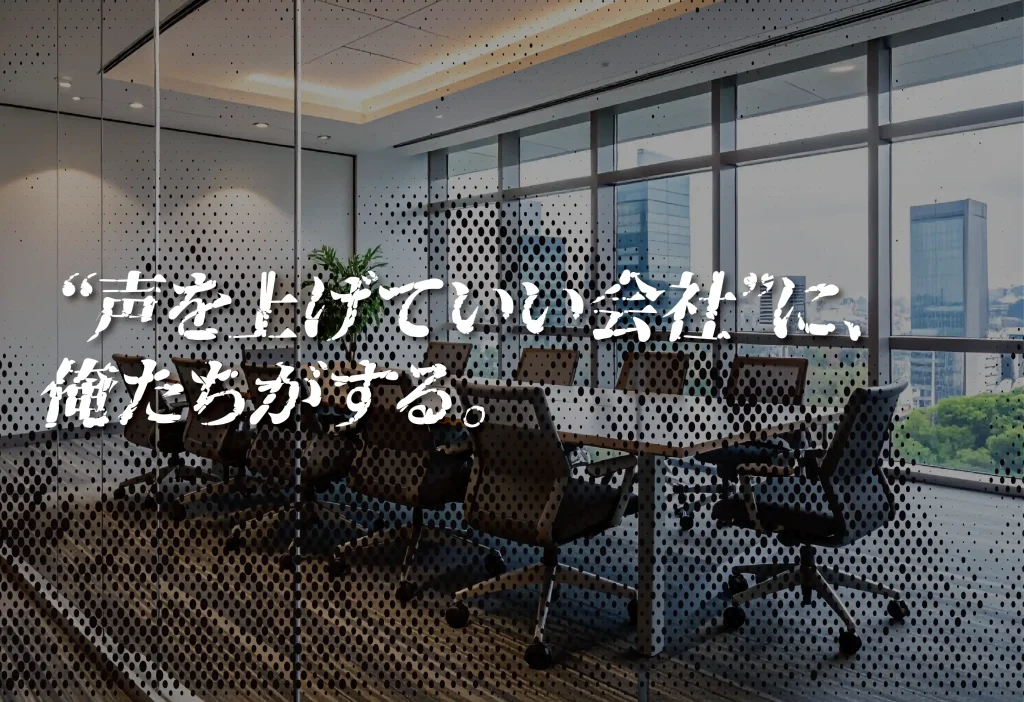
「“声を上げていい会社”に、俺たちがする。」
その文字を見たとき、私は、はじめてこの企業が“生きている”と感じた。
「信用」は、見抜くことではなく、築くこと
この物語を通じて、私たちが学んだことがある。
それは、信用は“目利き”で選ぶものではなく、“仕組み”で守るものだということ。
どれだけ華々しい実績があり、社内外の評判が高くとも、人の内面までは見通せない。
だが、信頼していたからこそ裏切られたのだとしたら、
次は「信頼を守るための枠組み」を先に作らねばならない。
私たちしえんグループの役目は、“不穏の兆し”を感じ取ることではない。
それが表面化する前に、“正直な声”が安心して届く道を作ることだ。
そしてこの企業も、いまその道を歩み始めた。
最後に
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
「盲点を突かれた組織の危機」。
それは決して他人事ではありません。沈黙は、組織を蝕みます。
ですが、声を上げる勇気と、それを受け止める構造があれば、
組織は再び歩き出すことができるのです。
私たちはこれからも、そうした企業の背中を、
静かに、しかし確実に支えていきます。

この記事へのトラックバックはありません。